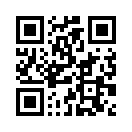2006年06月29日
マス コラボレーション

先週末から一昨日まで中津販促勉強会の皆さんとアラスカへ鮭漁とその加工工場の視察に行ってきました。2000年から続けているこの勉強会は本来個々の参加企業の翌月の販売促進施策を検討するものですが近年は活発に視察ツアーも行っています。北海道の農家めぐりや中国の生産現場をみなで周り新たな商品開拓をしたりしています。メンバー(大分県中津市の中小企業経営者)は互いに地域の消費者であり、地域活性化を志す同志であり、学校の先輩後輩であり友人です。講師は私一人ですがメンバーは相互に尊敬しあう非常に辛らつなパートナーとなっています。
パートナーであるというのは実際に商いの部分でも共同作業が発生しているからです。例えば今回のアラスカ視察は鮭の品揃え強化を進めている中小スーパーマーケット経営者であるメンバーに他のメンバーの一人が商いの顧客であるアラスカの水産会社を紹介することから始まっています。私を含む他のメンバーはそれに同行することで見聞を広げると共に紹介してくれたメンバーの得意(技術であり人脈であり)をより深く知ることができます。するとまた新たなビジネスの関係を想像することができます。事実アラスカを紹介してくれた彼にデンマークの商社を紹介してもらうことで大阪の私の顧客とまた別の取引も始まろうとしています。
一言で言えば仲間です。
仲間の問題意識は個々の経営から地域社会への貢献さらに地球環境改善の仕組みづくりへの貢献へと自然に広がってきました。
個々の課題が改善されるとともに自然に問題意識が深く広くなっていくのです。じっくりと。そして共通の問題意識が熟成されていくようです。互いに商いの中身は違いますが目指すところである問題意識のかなりの部分は共通であるのです。同じものを見て感じて勉強をし議論をするうちに一つの明確なベクトルが浮かび上がりそれを知らず知らず共有するようになっているのです。
業種も年齢も事業規模も違いますが、同時代に同じ地域に経営者として生きて共通の問題意識を持った仲間です。生涯の仲間でしょう。では僕は何でしょうか?経営コンサルタントとして雇われただけの職人でしょうか。同じ地域に住まない、経営者でもない。しかし問題意識の多くの部分は共有しているつもりです。やっぱり仲間でありたいのです。
役割分担や明確な数値目標以前に共通の問題意識をもった集団として仲間が生まれます。そして具体的なテーマに落とし込んだときに数値目標も生まれますしそれに伴って計画も作られるでしょう。
欲得だけだけで集まった集団のマスコラボレーション?成果報酬だけで集めた従業員?そこにまたお仕着せの経営理念?そこに仲間は生まれるでしょうか?
目標や理念を掲げると同時かそれ以前に同じ知識を共有する機会を持たなければ共通の問題意識は生まれないはずです。
事実かどうかサッカーの中田選手がいくら声高に説いても他の選手の練習量が増えなかったと言うような記事がありました。また来期監督を期待されるオシム氏は強化策として今までよりはるかに強豪チームとの練習試合を組むことをあげていました。目標だけではだめで問題意識を共有しなければそれなりの練習はできないし強くならないということでしょう。
Posted by なるほど! at 08:00│Comments(1)
この記事へのコメント
久しぶりのブログたのしみに待っていました。ブログもまた書いてる方の問題意識に触れるチャンスですね。
Posted by やまほん at 2006年06月30日 21:46